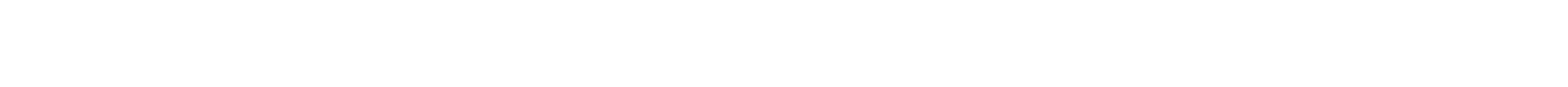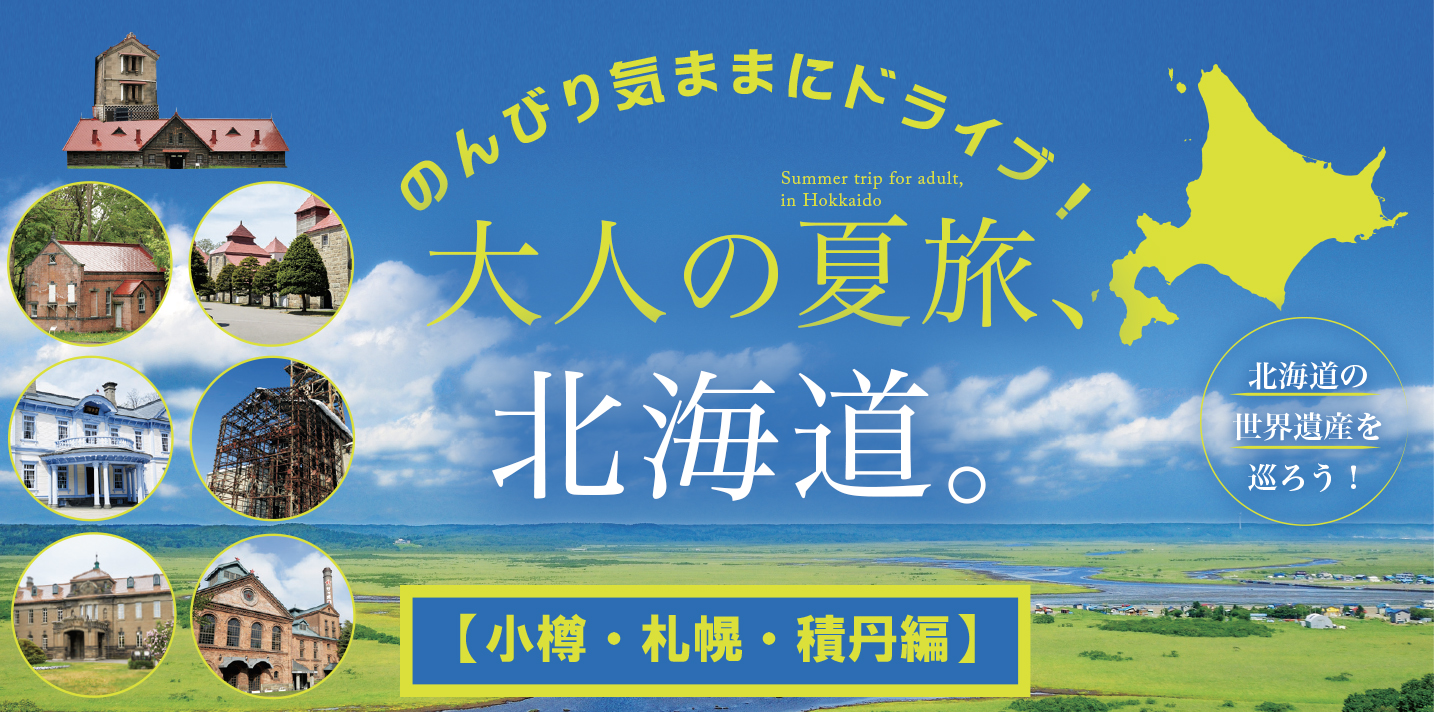大人の夏旅、北海道。【江差・函館・松前編】
北海道の中でも最も本州に近く、海に開かれた江差・函館・松前エリア。幕末から明治の歴史の面影を色濃く残し、国際貿易港として栄えた函館をはじめ道南エリアの北海道遺産を巡る旅へ。SPOT1 五稜郭と箱館戦争の遺構維新へ向け最後の戦いが繰り広げられた地五稜郭は幕末になり江戸幕府によって築かれた、火砲による攻撃に強い星型をした西洋式の要塞である。函館周辺の随所に残された国内最後の内戦の傷跡広大な北海道の中で本州に最も近い道南地域は、函館や松前といった町に代表されるように、歴史や文化が色濃く残されている。そんな道南地域にある北海道遺産には、様々な戦争の爪痕や貿易によって他国からもたらされた文化など、海に向かって開かれた土地ならではの特色が見られる。訪れてみればどこも、それぞれの時代の生活を肌で感じることができる遺産ばかりなのである。北海道の歴史を語るうえで欠かせないのが、明治元年(1868)10月から始まった箱館戦争だ。榎本武揚率いる旧幕府脱走軍艦隊が森町鷲ノ木に上陸し、箱館府があった五稜郭へ進軍。函館を基点にドライブを楽しむなら、まずは五稜郭を目指そう。そのルート上には褐色の山肌を天に突き出す駒ヶ岳と、周囲の景色を鏡のような湖面に写す大沼や小沼が織りなす素晴らしい景観が待っている。特に渡り鳥が羽根を休めるポイントである大沼は、時代を超えて人々の心を捉えて離さない。それは戦いに臨む兵士たちの目には、どのように映ったのかが気になってしまった。五稜郭に無血入城を果たした榎本らは、箱館政権樹立を宣言。しかし明治新政府は明治2年(1869)4月、乙部の海岸に軍を上陸させ反撃を開始。5月には箱館が戦いの舞台となる。「今年は箱館戦争終結から150周年の節目です。そのため市街随所に残る激戦地には順次、新たな案内板を設置している最中です」と、五稜郭タワー企画室長の木村朋希さん。五稜郭タワーは展望台に昇れば、特徴的な星型の稜堡式の城郭を一望することができる。それだけで満足するのではなく、市街地から港、山の方面へも目を向け、激戦地跡にも目を移す。町の景色を見渡すことで、函館山を中心に、函館が海へと突き出た両側に海が迫る独特の地形を持つことも再認識できるはずだ。戦いは今の函館市街だけでなく、江差や松前も含む道南一帯に及んでいるので、激戦の足跡をたどってみるもの面白い。ただし土方歳三が奮戦した二股口古戦場は、樹木に覆われた山深い地なので、クマとの遭遇に要注意だ。SPOT2 内浦湾沿岸の縄文文化遺跡群全国的にも珍しい「水場の祭祀場」を確認北黄金貝塚では、ひとつの集落に30人程度が暮らしていた。竪穴式住居には7~8人が生活していたとされている。全国的にもあまり例がない貴重な遺跡を間近で見る函館を出て車を内浦湾沿いに進める。室蘭市から函館市までの内浦湾(噴火湾)を囲むエリアからは、縄文時代から近世までの遺跡が数多く発見されている。なかでも縄文時代の早期(7000年前)から中期(6000~4000年前)のものとされる伊達市の「北黄金貝塚」では、大変貴重で興味深い遺跡が発見されている。「縄文文化は”自然と共生”したものと思われがちですが、意外に大量のウニ、カキやホタテなどの採取も行っています。それでも自然環境が保たれたのは、貝塚を全ての生き物の墓地として捉え、そこに人間も埋葬することで、自分たちも自然の一部だということを忘れずにいる。だから必要以上の獲物を取らないという考えが生じ、極端な自然破壊を防いだのだと考えられます」伊達市噴火湾文化研究所の永谷幸人さんは、貝塚は単なるゴミ捨て場ではなく、縄文人にとって神聖な場所であったと語る。そしてそんな貝塚の断面を見ると、様々な動物や魚介類の骨や殻などが交互に積み重なっていた。小高い斜面上にある貝塚からは、目の前に内浦湾が広がり、かすかに潮の香が鼻孔をくすぐる。弓なりに続く陸地は緑に覆われ、今でも豊かな自然に恵まれていることが実感できる素晴らしい地だ。さらに永谷さんは全国的にほとんど例を見ない「水場の祭祀場」にも案内してくれた。遺跡内には縄文時代から変わらずに湧き出ている水場がある。その周囲からは、壊された石の道具がこれまで1200点以上も発見されている。「役目を終えた道具は、壊すことで完全にあの世へ送ったことになったのではないか。それが水が生まれる神聖な場所に納めることで、道具への感謝と再生を祈っていたのだろうと考えられているのです」北黄金貝塚は「北海道・北東北の縄文遺跡群」として世界遺産への登録を目指しており、これからますます注目されるだろう。SPOT3 函館西部地区の街並み明治の面影を色濃く残す通りと建築物末広町電停と大町電停間を走る函館市電800形電車。背後に見えるグリーンの建物は大正2年(1913)築の相馬株式会社社屋。瀟洒な洋館とレトロな路面電車が一幅の絵画にそして、函館へ再び戻って市内へ。安政6年(1859)、日米修好通商条約に伴い箱館港は横浜港、長崎港と共に日本国内初の国際貿易港として開港された。この町は古くから北海道への玄関口であったが、幕末にはいち早く西欧文明を迎え入れる窓口となったのである。現在の函館市街地は内陸部へと広がっているが、もともとの町は函館山麓の、西部旧市街と呼ばれているエリアであった。旧市街には函館山に向かって何本も南北の道がある。その中に「基坂(もといざか)」と名付けられた、ひときわ広い坂道が存在する。坂の上から見下ろすと、まずは海と船が織りなす絵画のような美観に目を奪われる。箱館が貿易港として開港すると、基坂の下に運上所(後の税関)、坂の上には奉行所が置かれた。その名の通り、この坂は町の中心だったのだ。奉行所の跡地には明治43年(1910)9月20日、旧函館区公会堂が開堂する。現在はこの瀟洒な洋館を中心に、一帯は元町公園として整備されている。さらに公園周辺には、和洋折衷の洒落たショップや住宅が建ち並び、格好の散策スポットとなっている。この日は平日だったが、大勢の観光客の姿があり、活気にあふれていた。また函館ハリストス正教会、カトリック元町教会、函館聖ヨハネ教会、真言大谷派東本願寺函館別院という、異なる宗教が肩を並べて建つ、不思議な光景にも遭遇する。これも国際貿易港を持つ、開放的な空気に満ちた函館らしい。坂の上から海側を見下ろすと、港を借景にして走り過ぎる路面電車の姿が見られる。北海道で路面電車が走っている町は函館と札幌だけだ。函館市電は明治30年(1897)12月に馬車鉄道として産声を上げた。そして大正2年(1913)6月には電車化。それは東京以北で初の、路面電車誕生の瞬間であった。函館に遅れること5年、札幌の路面電車は大正7年(1918)に運行を開始。いずれも「まちの顔」となり、現在も両市民の足として活躍している。特に函館市電は古い車両も多く、それが明治期の佇まいを残す街並みを背景に走る姿が、見る者の心に郷愁を抱かせる。車を使った旅であっても、少しの間は駐車場に預け、電車旅を味わってみるのも悪くない。運が良ければ復元されたレトロ車両「箱館ハイカラ號」に遭遇できるだろう。SPOT4 函館山と砲台跡明治後期に要塞化され津軽海峡を防備した実戦を経験することなく、大砲が撤去された砲台跡。軍事施設が生み出した思わぬ副産物に感謝函館という町の特徴を成すのが、海に突き出した標高334mの函館山だ。この山頂から眺める夜景は、日本に関する旅行ガイドである『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』で、三つ星として掲載されている。夜景の時間ではなくても山頂から函館市街を一望しようと、大勢の観光客が山頂展望台に集まっていた。だが函館山には、まるで観光客には気づかれたくないかのように、うっそうと茂った木々の中に軍事施設が隠れている。これは明治31年(1898)から4年の歳月を費やし築かれた函館要塞跡で、当時、戦争状態に陥ることが予測されたロシアの艦隊から、造船所が置かれていた函館港と、津軽海峡を守備するために築かれたものだ。だが要塞は一度も実戦を経験することなく、昭和20年(1945)の太平洋戦争終戦と共に砲台や台座などは撤去。コンクリート土台や煉瓦の壁だけが残った。と共に軍事機密を守るために立ち入り禁止だったことで、手つかずの自然も残された。要塞周辺は約600種の植物、約150種の野鳥と遭遇できる。途中の駐車場からはアップダウンも少なく、山道の四方に海が見える景色も飽きないので、ドライブでなえた足には、格好のハイキングコースなのだ。SPOT5 上ノ国の中世の館和人とアイヌの混住説を裏付ける墳墓発見勝山館を築いたのは、松前藩の祖とされる武田信広と伝えられている。夷地のユートピアで和人とアイヌ民族が共存函館から約1時間30分。見渡す限り緑のグラデーションがまぶしい樹木に覆われた山中を抜ける道を走り続ける。そしてやってきた上ノ国は、日本海に面した小さな町であった。わずかな平地の周囲には低山が折り重なる。そのひとつ、標高159mの夷王山からは、1470年頃に築城された山城「勝山館」跡が発見された。弓なりの海岸線を一望する城跡からは、200戸近い和人とアイヌ民族が暮らしてきた痕跡があった。「館の背後から見つかった約650基の墳墓からは、和人の墓の間にアイヌ民族の墓が確認されています。それまで言われてきた和人対アイヌ民族という対立図式は、ここでは当てはまらないのです」上ノ国町教育委員会学芸員の塚田直哉さんの話を伺いながら素晴らしい景観を眺めていると、この城が理想郷に思えてきた。SPOT6 福山(松前)城と寺町最後の日本式城郭と道内唯一の近世的寺町奥は外観が復元された松前城天守と火災を免れた本丸御門。こちらは国の重要文化財。開拓以前の姿を伝える北海道で唯一の和式城郭最後に、道内唯一の日本式城郭が残る松前へ。福山城が竣工したのは幕末の安政元年(1854)。そんな時期に城が築かれた理由は、ロシアやアメリカなどの船舶が、日本海に出没するようになったことから。幕府は北方警備を目的に嘉永2年(1849)、松前崇廣に福山館の改築を命じたのだ。その結果、完成した城は最後期のもので、かつ北海道内唯一の日本式城郭となった。領民は親しみを込めて松前城と呼んだ。城の北側には、これも道内で唯一の近世的な寺町が残る。現在は江戸時代の本堂や庫裏を残す龍雲院をはじめ5つの寺院と歴代松前藩主の墓所が、木立に囲まれた静かな一角に集まっている。城跡から寺町界隈を散策していると、まるで信州あたりの城下町を散策している錯覚に陥る。古木に囲まれた参道からは、荘厳な空気と歴史の重さが感じられた。こうした気持ちを抱かせてくれるのも、北海道の懐の深さであろう。「箱館戦争や太平洋戦争を経ても、無事だった天守は、残念ながら昭和24年(1949)、城跡の麓にある役場で起きた火災で類焼してしまいました。」(松前町教育委員会主査・佐藤雄生さん)それでも、今も美しい日本の風景が残されている松前町。開拓使以前の北海道の姿を知りたければ、ぜひ松前町は訪ねてほしい。※こちらは男の隠れ家2019年8月号より一部抜粋しております
もっと読む