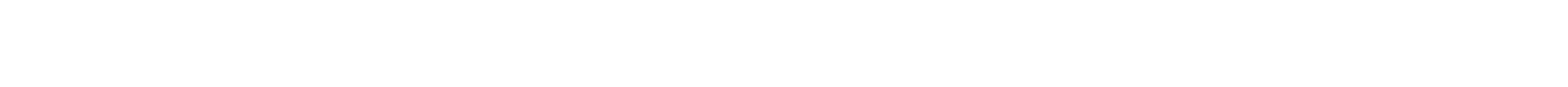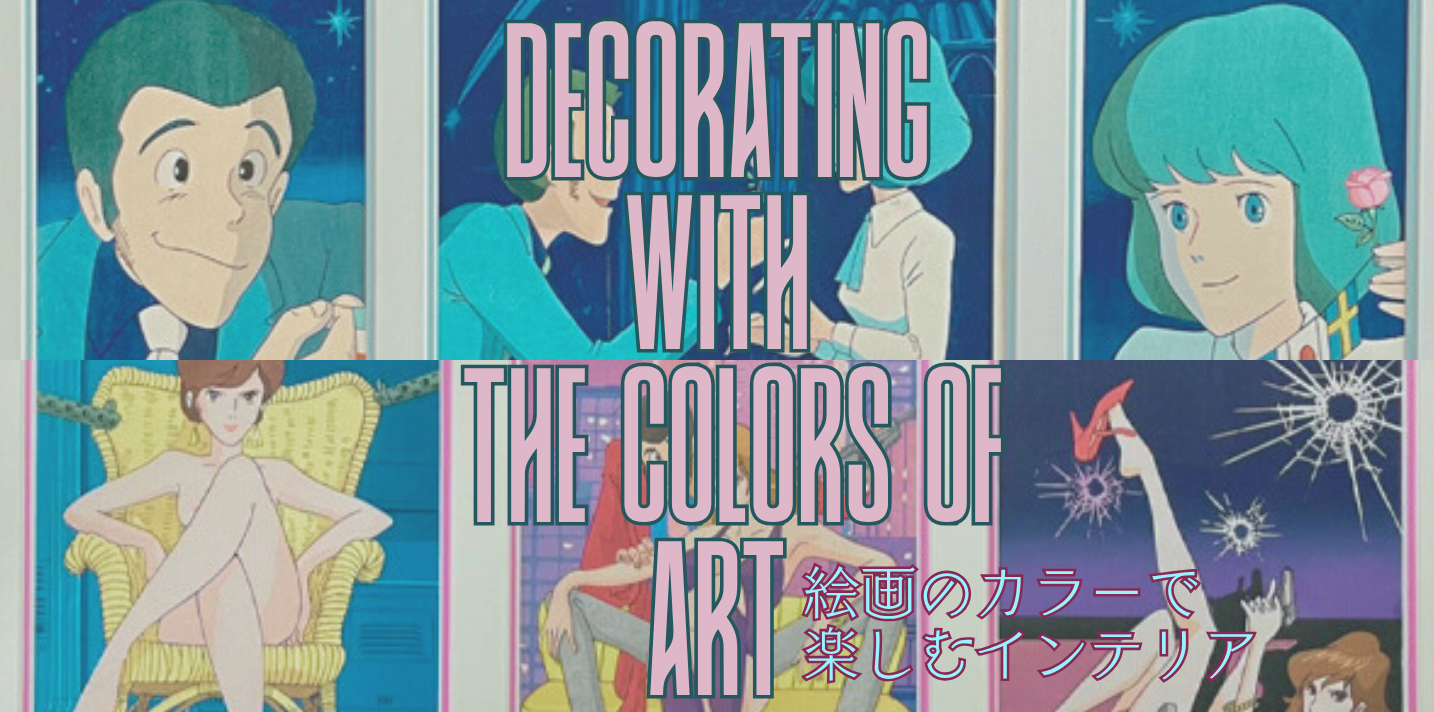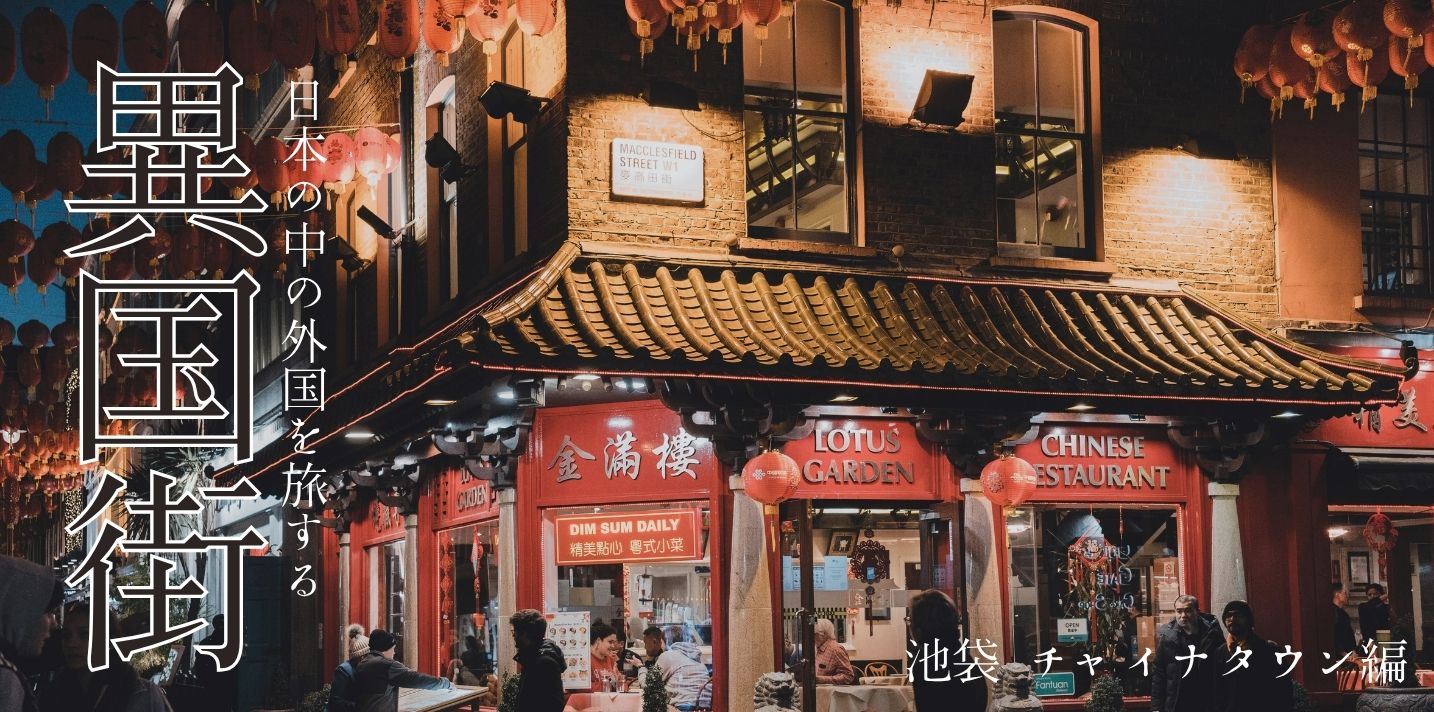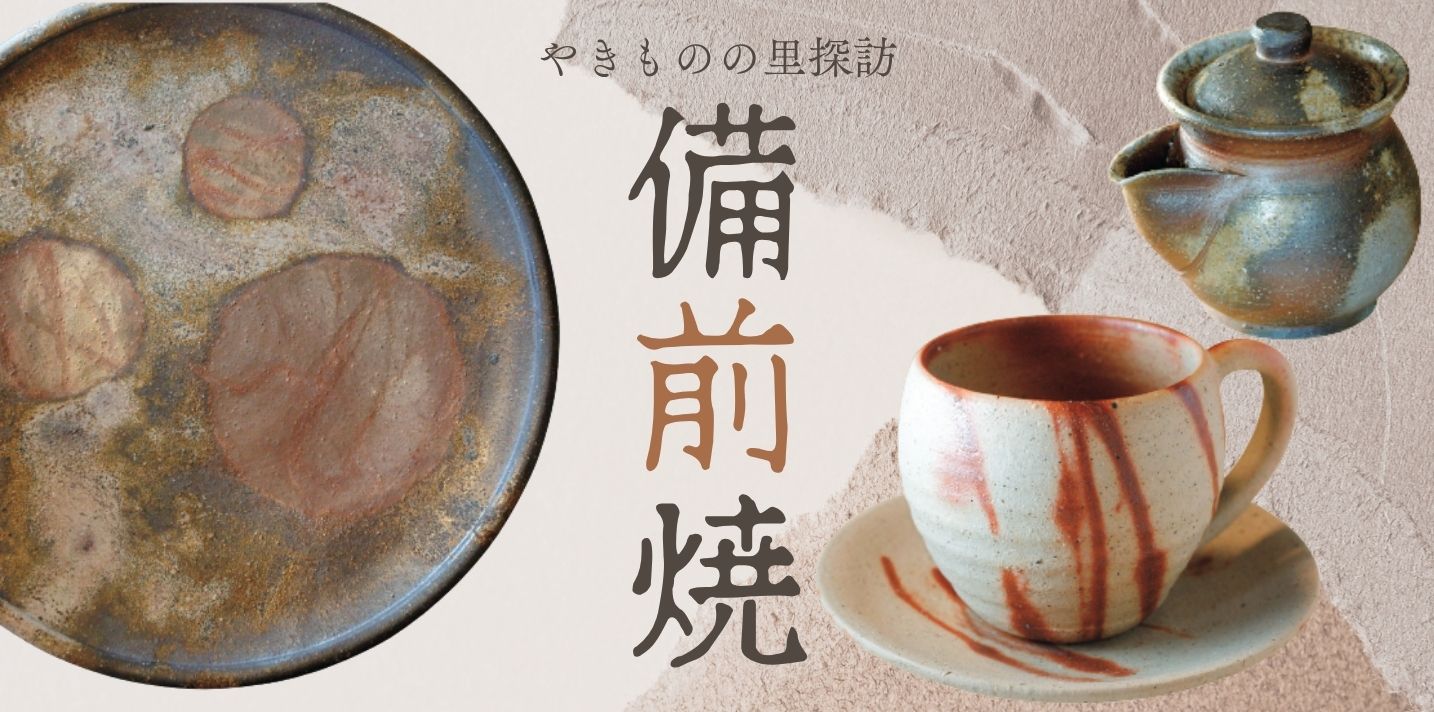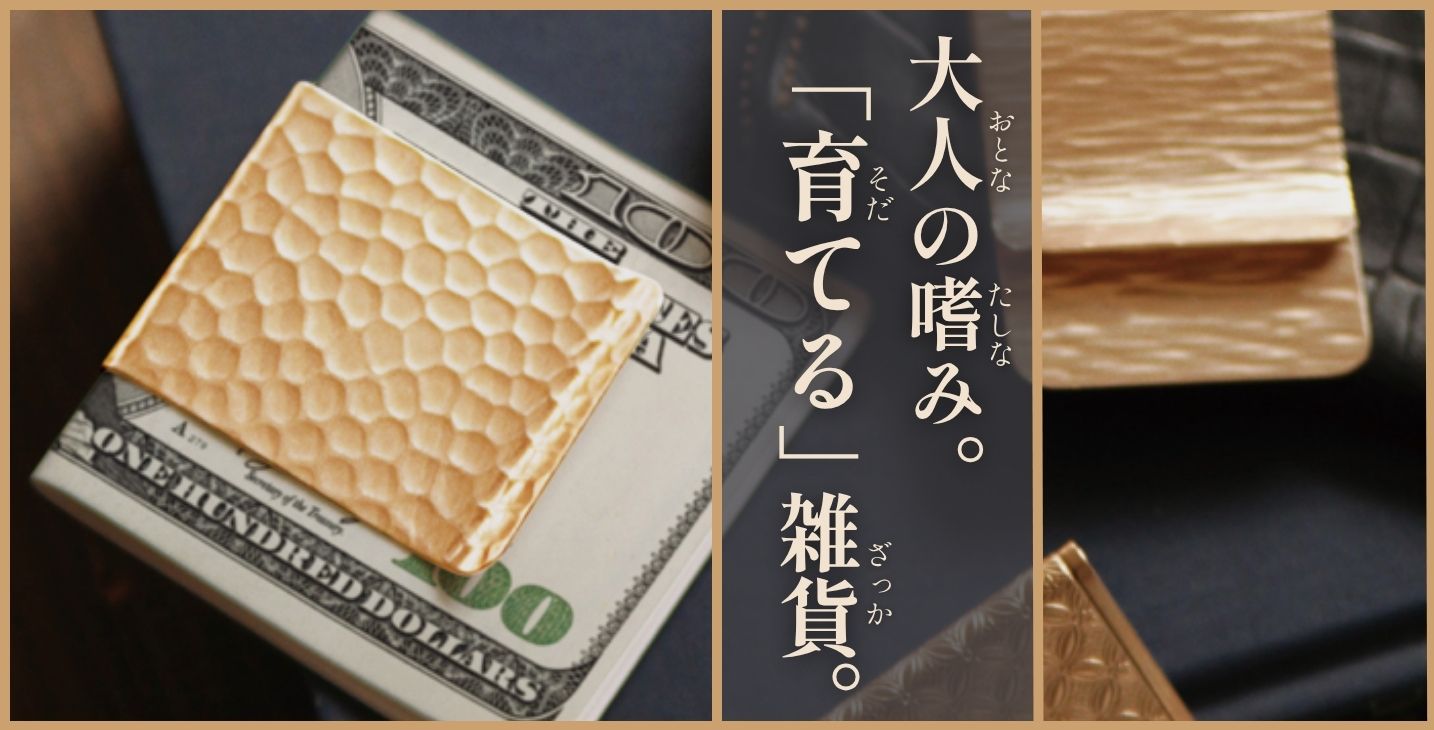【3大グルメ企画】 第五章「カリーライス専門店 エチオピア」編
【3 大グルメ】は、日本人が大好きな人気グルメ「ラーメン」「カレーライス」「ハンバーガー」を提供する、こだわりの飲食店を紹介していきます。セレクトのポイントは「老舗」と「老舗店主のおすすめ店」。今回は神保町で 40 年のカレー専門店をピックアップ!街に愛されるスパイシーカレーの味とは?!コーヒー屋から始まった、“スパイシーカレー”専門店?!カレー激戦区・神保町で、40 年近く続くカリーライス専門店「エチオピア」。もともとはコーヒーを出す喫茶店だったというこのお店、あまりにもカレーが人気だったことからカレー専門店へとシフトしたというから驚き。店名の由来はコーヒー豆発祥の地・エチオピアだが、今やこの名前で思い浮かぶのはスパイス香るあのカレーという人も多いだろう。昭和 63(1988)年からこの地で営業を続ける神保町本店。平日はビジネスマンや学生、観光客が次々と訪れ、ピークタイムには 100 食以上が注文されるほどの盛況ぶりだ。10〜100 倍まで OK!「辛さ」が選べる無限スパイスワールドエチオピア名物といえば、注文時に選べる“辛さのレベル”。0 倍(辛くない)から始まり、上限はなんと 100 倍まで!常連の中には、裏メニュー的に 100 倍カレーを頼む強者も。店員さん曰く、「表に出していないけど、言ってくれたら OK」とのこと。この辛さはただ単に唐辛子の量を増やしたものではなく、スパイスのブレンドで調整されているため、辛いだけでなく奥深い旨みと香りが広がるのが特徴。口の中が燃えるようでいて、後味は意外にもスッキリ。クセになる味わいで、リピーター続出中だ。野菜・豆・チキンが三大人気!迷ったらまずこの3 種をメニューはビーフ、チキン、野菜、豆など多彩。中でも人気が高いのが「豆カレー」「ビーフカレー」「野菜カレー」の 3 つ。豆カレーは、スパイスと豆の相性が抜群で、滋味深さにほっこり。ビーフカレーは王道ながら、ルーとの一体感が秀逸で、食べ応えもバッチリ!野菜カレーはごろっとした具材の存在感があり、ヘルシー志向の方にも好評だ。胃の調子を整えてくれる、スパイスが効いた、体が「元気になる」と評判のエエチオピアのカレー。まさに“エナジー系”カレーといえる一皿だ。カレーの後のマンゴープリンの優しい甘さがたまらない!カレー激戦区・神保町で生き残る理由とは?エチオピアがここまで長く愛され続ける理由は、スパイスや調味料の辛さと細部まで作り込まれたバランスの良さにある。素材の選定、調理のタイミング、盛り付け…そのすべてが「うまさ」に直結している。店主曰く、エチオピアは特に”スピード重視”なのがポイントなのだという。混雑するランチタイムでも驚くほどスムーズにカレーが提供されるのは、厨房内の連携と段取りの良さのたまもの。席数は 1 階が 10 席、2 階が 24 席。回転の早さも、リピーターが多い理由のひとつだろう。エチオピアは、テイクアウトも可能で、レトルトカレーも販売中!スパイスの効能まで明記されているのもありがたい。スパイスと人が交差する場所で、記憶に残る一皿を。インタビューの最後、「これまでで一番うれしかったことは?」という問いに、「この味でお客さんがまた来てくれること」と答えてくれた店主さん。仕込みから営業まで、決して楽ではない日々。それでもお客さまから「また来たい」と言ってもらえることが、何よりの励みになっているという。ひと皿のカレーに、40 年分の工夫と誇りが詰まっているエチオピア。今日もまた、神保町の街角でスパイスの香りが漂っている。-----------------------------------Shop dataカリーライス専門店 エチオピア 東京都千代田区神田小川町 3-10-6電話/03-3295-4310営業時間/月〜土 1F 11:00〜22:30(ラストオーダー22:00)、2F 11:00〜21:30(ラストオーダー21:00)日・祝日 1F 11:00〜21:00(ラストオーダー20:30)、2F 11:00〜20:30(ラストオーダー20:00)年中無休アクセス/JR 中央線お茶の水駅より徒歩 5 分、東京メトロ神保町駅より徒歩 5分
もっと読む