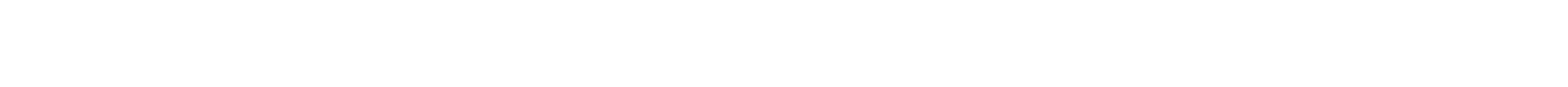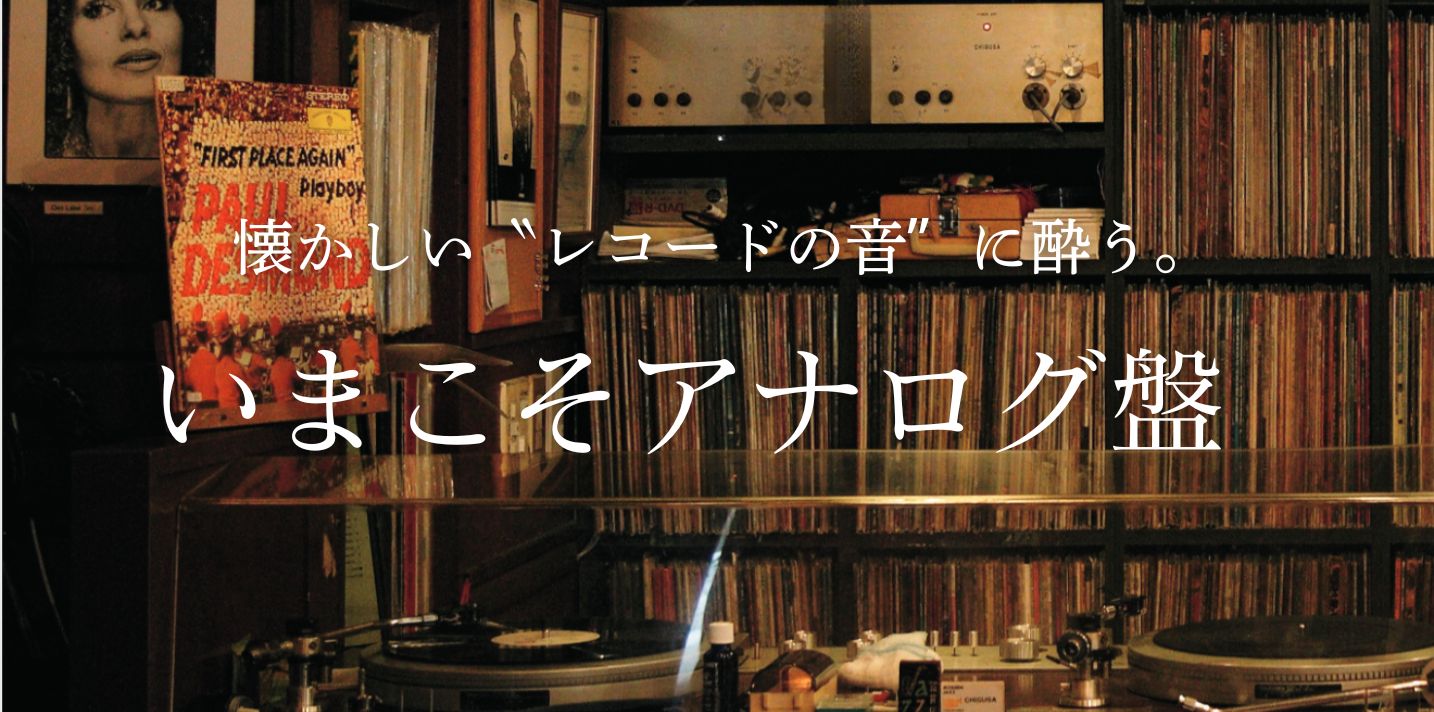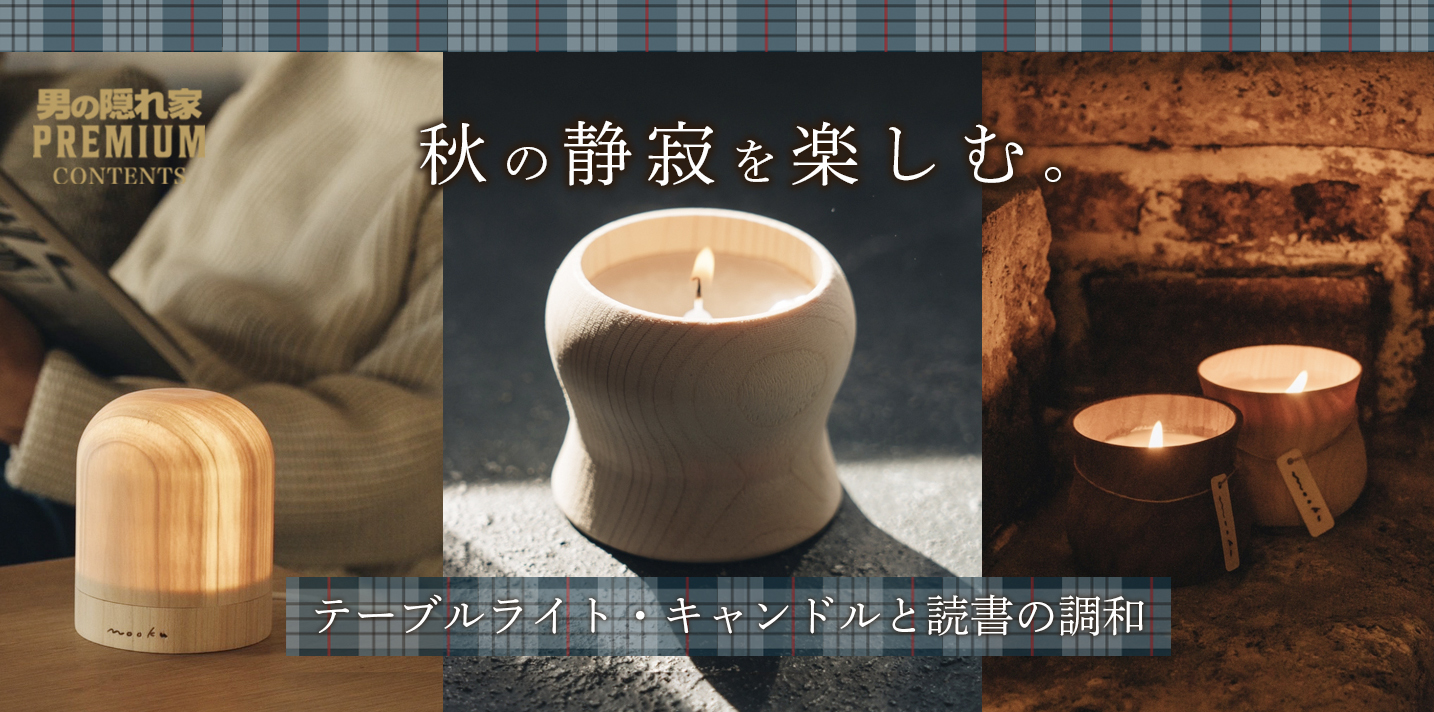古民家でのんびり。自然と親しむ日。
日々の喧騒から少し離れ、自然に囲まれた場所で過ごす一日は、心と身体をじんわりと癒してくれる特別な時間である。都会の生活ではなかなか味わえない、鳥のさえずり、風に揺れる木々の音、土や草の匂いに包まれるそのひとときは、人間が本来持っていた自然とのつながりを思い出させてくれる。古民家には、長い年月をかけて培われた落ち着きと、都会に慣れた人でも懐かしさを感じさせる空気がある。木のぬくもり、優しい質感、障子を通して差し込む柔らかな光――それらの要素が、知らず知らずのうちに心をほぐしてくれるのである。縁側でお茶を飲みながら、季節の移ろいを感じるだけでも、極上のひとときとなる。自然の中の古民家は、疲れやすい現代人へのよい影響も。自然の中で過ごすことには、科学的にも多くの効能がある。森林浴にはストレスホルモンの減少、免疫力の向上、血圧や心拍数の安定化といった効果が認められており、心身のバランスを整える働きがあるとされている。とりわけ、スマートフォンやパソコンから離れ、自然のリズムに身を委ねることで、脳が「休息モード」に入り、創造力や集中力が高まるという報告もある。古民家での一日は、特別なことをする必要はない。薪で火を焚き、ご飯を炊く。採れたての野菜を使って料理をする。昼下がりにはハンモックで読書にふける。そうした何気ない時間の積み重ねが、現代人の疲れた心をやさしく包み込んでくれるのである。自然の音を聞きながらゆっくりと深呼吸をすることで、自律神経の働きが整い、睡眠の質も向上する。夜には満天の星空を見上げ、静けさの中に身を置くことで、また明日への活力が湧いてくるはずだ。忙しい毎日だからこそ、「何もしない贅沢」を味わう時間が必要である。古民家で自然とともに過ごす一日は、忘れかけていた本当の豊かさを思い出させてくれる、かけがえのない体験となるであろう。「何もしない贅沢」を。古民家ゲストハウスで癒しのひととき。男の隠れ家PREMIUMより、古民家での素敵な体験をご提供。世界中をバックパックで旅して回ったオーナーの三髙菖吉さんが、「最初は適当にDIYが楽しめればと思って見に来たのですが、言葉に表せないほど素敵な梁をみた瞬間、すっかり惚れ込んでしまいました」という、築140年を越える古民家。そこで多くの人に快適な里山ライフを体験してもらおうと、ゲストハウスにリベーションし、「ゆる宿Voketto」として生まれ変わらせた。「ゆる宿Voketto」は、古民家の味わいを随所に生かしつつ、快適な一夜を過ごせる設備が充実。しかも清潔感にあふれているので、老若男女問わずに安心して利用できる。滞在しているだけでも、奥静岡の豊かな自然を堪能でき、「男の隠れ家限定プラン」には、ヨコザワテッパンポケット、川根本町産鹿肉ソーセージ、焚き火体験がセットされている。ちなみに食事は別料金で朝晩ともお願いすることもでき、キッチンを使って自分で楽しむことも可能。自由に過ごせるのも魅力。満天の星空や目に優しい焚き火体験が味わえる。泊まりたい人数に合わせて、8畳和室と16畳和室が選べるのもポイント。生まれた場所も年齢も違う人たちが集まって、お酒を飲みながら語り合う。そして、日々の喧騒から離れて本当の素直な自分に立ち返る。そんな場所をつくりたいと思い、生まれたゆる宿Voketto。ゲストハウスは木の温かみを感じる雰囲気で、オーナー手作りのテーブルやこだわりのものが飾られている。室内は昔ながらの雰囲気は残しながらも、快適に過ごすことが出来るようにリノベーションしてある。とにかくゆっくりと、心を開放して過ごせる。心をほどく、静かな時間。自然の中、古民家で過ごす一日は、自然と調和しながら自分自身を見つめ直すひととき。忙しさを手放し、本来の自分を取り戻す時間となるだろう。--------------------------------------------------商品詳細ゆる宿Voketto【男の隠れ家限定】古民家ゲストハウス利用権[16畳和室]28,000円 (税込)>>商品をチェックゆる宿Voketto【男の隠れ家限定】古民家ゲストハウス利用権[8畳和室]9,500円 ~ 26,000円 (税込)>>商品をチェック
もっと読む