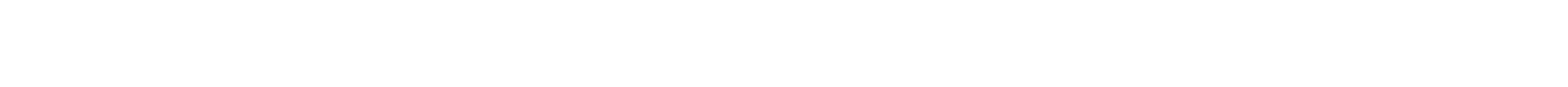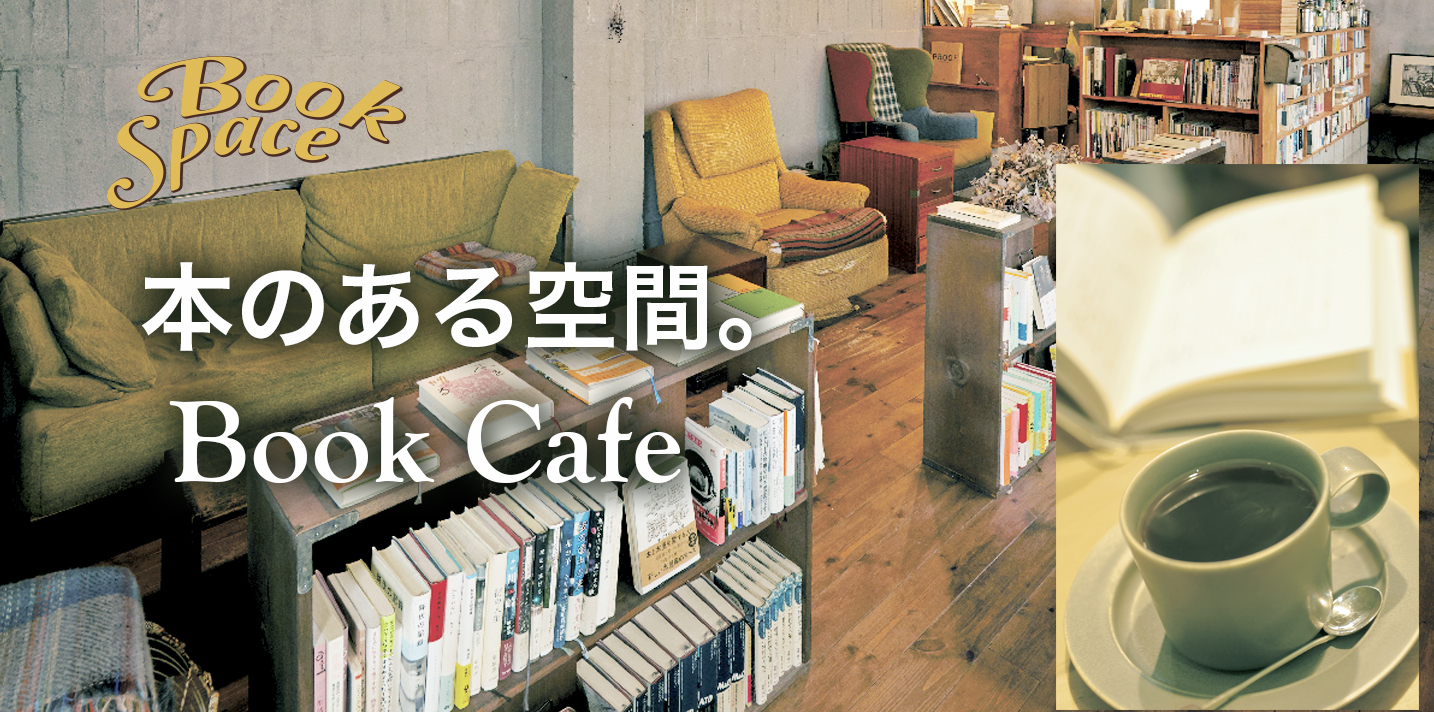【3大グルメ企画】 第三章「FUNGO 三宿店」編
日本人が大好きな人気のグルメ「ラーメン」「カレーライス」「ハンバーガー」を提供する飲食店をご案内していく【3大グルメ】。今回は、ハンバーガーショップの草分け、FUNGO 三宿店を、料理芸人としてバラエティ番組やラジオ等に出演し、YouTube でも人気を博している「藤井21」さんがご紹介します。地元ローカルにこよなく愛される味をどうぞ!都会の喧騒を離れてゆったり落ち着けるバーガーショップへようこそ。渋谷や三軒茶屋の喧騒を離れるだけで緩やかな時間の流れる住宅が建ち並び、遠くからテニスボールを打つ音が聞こえる公園には静かな緑が広がっている。ここには国道 246 を走る車の喧騒も聞こえてこない。池尻方面から世田谷公園を抜け、学芸大学方面向かう。「平日の午前中からテニスとは優雅ですな」と、誰に語るでもなく小さくつぶやきつつ午前中の涼しい風を感じ歩く。世田谷公園を抜けるとちょうど目の前の交差点を挟んで斜向かいに、真っ青な壁の建物が目に入る。鮮やかなオレンジ色の店名が、真っ青な壁にくっきりと映え、赤と白のストライプのサンシェードも相まって目のスクリーンにインパクトを残す。この地で“東京ハンバーガー御三家"のひとつ「FUNGO 三宿本店」は今年の12月で創業 30年を迎える。店前のテラス席にはスチール製の真っ赤な椅子と丸テーブルが数脚並び、店内に入ると木製のテーブルと椅子が綺麗に配列されている。壁は生成りの塗装に外装と同じ真っ青な腰壁の羽目板。和食店にはない色味にアメリカンを感じて少しだけワクワクしてくる。「せっかくだしテラス席で優雅にバーガーでも決めてやろうか」とテラス席に座る。少しだけ三宿の雰囲気にあてられたみたいだ。テーブル上にはカトラリーと紙ナプキン、使い切りのケチャップとマスタード、そして紙エプロンが置かれている。〜ハンバーガー?サンドイッチ?〜卓上のメニューを開くと先ずサンドイッチがずらりと幅を利かせている。「シュリンプとアボカド」「スモークサーモンとクリームチーズ」「自家製ベーコン・レタス・トマト」まあどれもワクワク感をそそられる具材だ。今でこそ定番の具材となったアボカドも創業当時は日本では扱っているお店は少なかったそうだ。オープン初期から人気のエビアボカドサンドウィッチ ¥1,350FUNGO 三宿本店は創業したオーナーがアメリカ留学時に食べたサンドイッチの味が忘れられないと、日本に帰ってきてからその味を再現して始めたお店らしい。つまりハンバーガー御三家の一角のルーツはサンドイッチにありということだ。…ん?ハンバーガーとサンドイッチって何が違うんだ?ふとなんとなく気になって違いを調べてみると、サンドイッチはパンに様々な具材を挟んだ料理で、ハンバーガーはバンズ(丸いパン)を切って肉類や野菜を挟み込んだものだという(※1)。どうやらハンバーガーはサンドイッチファミリーの一員らしい。ということは FUNGO のハンバーガーはサンド料理界の基礎をしっかりと押さえているということになるじゃないか。サンドイッチに少しだけ心惹かれつつも今日の目的はハンバーガーだとメニューをめくる。「クラシック」「アボカドタルタル」「自家製ベーコンチーズ」メニューに載っている写真も相まって香り立つようなラインナップにどれを選んでいいか考えこんでしまう。これは永遠に迷いかねないのでえいやと勢い一発「自家製ベーコンチーズバーガー」をチョイス。ご多分に漏れず“自家製”という言葉に惹かれてしまっている。自家製ベーコンが入った人気のベーコンチーズバーガー¥1,960カウンター越しにオープンキッチンを覗くと、鉄板の上でパティを焼きながらバンズを半分に切りつつフライヤーでポテトを揚げる。野菜やソースを準備し、流れるような手さばきで調理を進めている店長の関さんは27歳の若さでFUNGO 三宿の店長を任されている。「自家製ベーコンチーズバーガーです」と、関さんが爽やかな笑顔で出してくれた。〜大ご馳走の味〜白の丸皿にはデカデカとハンバーガーが立ち上がっている。茶褐色のバンズの間には下からゴツゴツした分厚いパティ、そしてとろけたチーズがパティを包み込み、その上にこれまた分厚い自家製ベーコンが折り重なっている。そして瑞々しいレタスにトマトの断面がチラリと顔をのぞかせる。そんなバーガーは脇には黄金色にカリッと揚がったポテトが寄り添っている。バーガーには「FUNGO」と書かれた小さな旗が誇らしげに立っている。まるでそれぞれの具材が主張しながらも“ちゃんと一緒に食べてくれよ”と言っているかのようなそんな出で立ちだ。シズル感のお手本のような見た目に、これはたまらんとばかりにテーブルの隅に置かれたナイフとフォークにガン無視を決め込んでハンバーガーを両手で持ち上げかぶりつく。もちっとしたバンズと共に具材も一緒に噛みしめる。レタスの歯触りが小気味よく、粗挽きの肉々しいパティからじゅわっと旨味が染み出してくる。直後にスモーキーな自家製ベーコンの香りとチーズの濃厚な味わいが広がり、トマトの瑞々しさが口の中をさっぱりとさせる。…あぁこれは笑っちゃうくらいに旨い。バンズやそれぞれの具がしっかりと存在感を示しながらも一つに調和している。ベーコンだけだと燻製感が前に出すぎるし、パティだけだと肉々しさが粗すぎる。でも、それらが一緒になると、不思議とハンバーガーというひとつの料理になる。これはちゃんと計算されている料理だ。FUNGO 三宿では毎朝開店前に野菜が届きグラム単位で量を調整して、その一口のための最適な分量になるよう切り分けられているらしい。もちろんパティも同じだ。粗挽きのミンチは噛むたびに肉感を感じられるように脂と赤身のバランスを見極めて特注していて、こね方から焼き方まで細やかな工夫が詰まっているのだとか。そして全体をふんわりと受け止めているのが特注しているというバンズだ。「峰や」さんに特別に焼いてもらっているというこのバンズは、もっちりとした弾力で甘味がありつつも香ばしい。試しにバンズだけ千切って食べてみたが美味しい、おいしいが確かにもっちりした食感が立ちすぎていて少しだけ重たい印象がある。しかしこれがハンバーガーになると不思議と調和している。“挟まれることを前提にしたパン”なのだろう。この料理は別々の具材が一つになって完成している。それを頭ではなく口の中から身体が納得させられているようなそんな理屈抜きで旨いと思える味だ。オーナー曰く「特別なことをやっているわけじゃないんです。100 年後も続くお店をやりたいんです」と。確かに奇をてらったような具材があるわけではないが、食材にこだわり突き詰める。FUNGO 三宿はサンドイッチというハンバーガーの基礎があり、ひとつひとつの食材にこだわり続けるからこそ、ここまで 30 年続きそしてきっとこの先 70 年、その先も続いていくのだろう。そんな完成されたハンバーガーでも個人的に唯一足りないものがあることに気づいてしまった。キンキンに冷えたビールだ。グラスの表面にはうっすらと細かい水滴が浮かんでいる。ハンバーガーの余韻が口の中に残るうちに生ビールを一気に流し込む。そうそうこれなんだよ…。パティの旨味、ベーコンの燻製香、そのすべてにビールがピタリと寄り添ってくる。かぶりついてはビールを一口、もう一口と手が止まらなくなる。これはもう“うれしい大ご馳走”だ。生ビール(ハイネケン) ¥700 とベーコンチーズバーガー¥1,960〜万人に愛される味〜ふと顔をあげると奥の窓際では、一人でやってきた様子の女性が、スマートフォン眺めながら提供を待っている。常連客に見えるやや年配の男性はハンバーグを黙々と頬張り、店の入り口にはテイクアウトを待っているであろう男性がいる。この店には三宿の穏やかな時間と空間がしっかりとあり、ふらりと立ち寄れる雰囲気を感じる。帰り際にレジの後ろに何十個も積み上げられたテイクアウト用の紙箱が気になって「この箱の量を一日で全部使うんですか?」と聞いてみた。「これは今日たくさんデリバリーの予約が入ってまして、常連さんがよく頼んでくれるんです」この大ご馳走はわざわざ食べにくる価値がありながら、どこでも楽しめる味でもあるんだな。オープン直後からぽつぽつとお客さんが入りだした店を後にする。キッチンの中では関さんが次々とパティを焼いている。もう少しだけこの三宿の緩やかな空気でも感じながら帰るかと歩き出す。もちろんテイクアウトの紙箱に入ったサンドイッチを持って。・コーラ ¥500 とカリフォルニアバーガー ¥1,900・コーラ ¥500 とクラシックハンバーガー ¥1,400※1:Weblio 英和辞書Shop dataFUNGO 三宿店東京都世田谷区下馬 1-40-10電話/03-3795-1144営業時間/11:00-21:00(last order 20:00)定休日/無休、年末年始(12/31〜1/2)
もっと読む