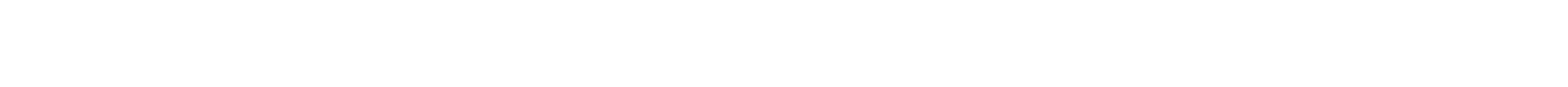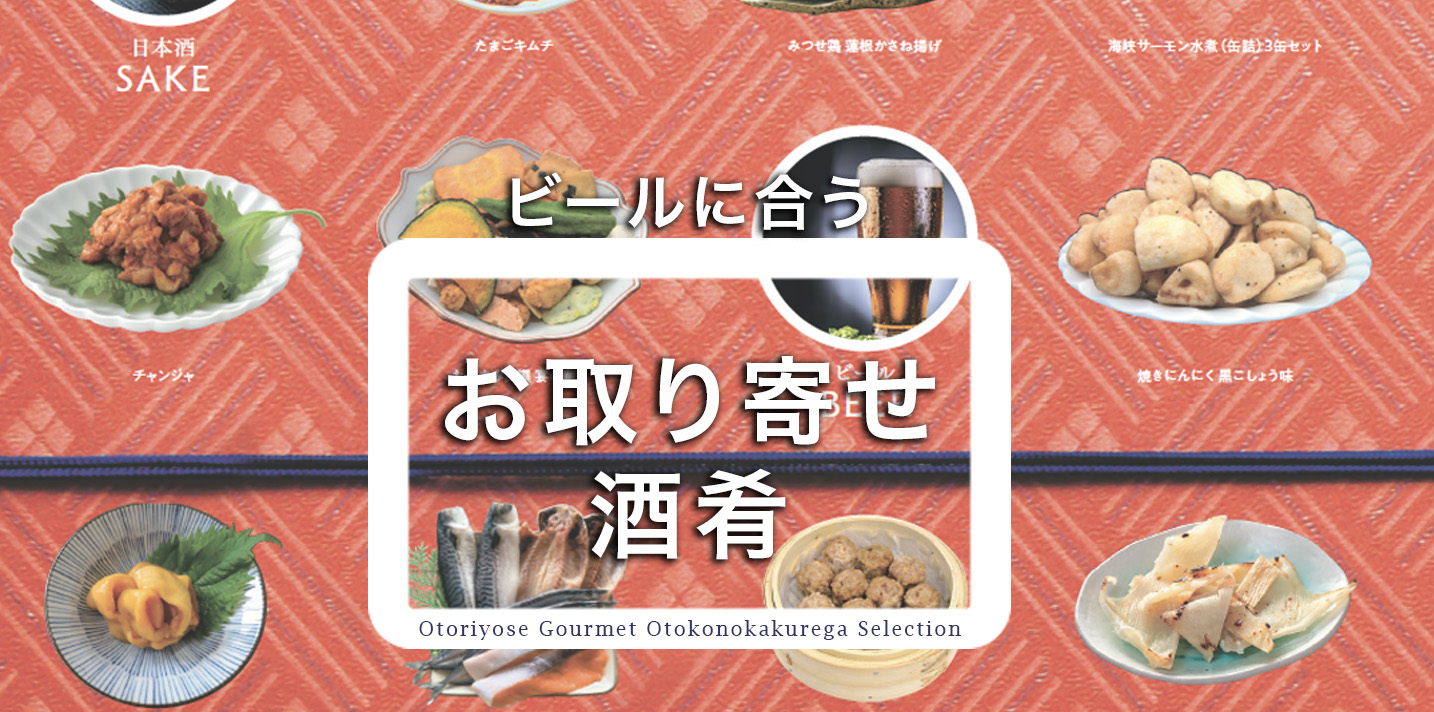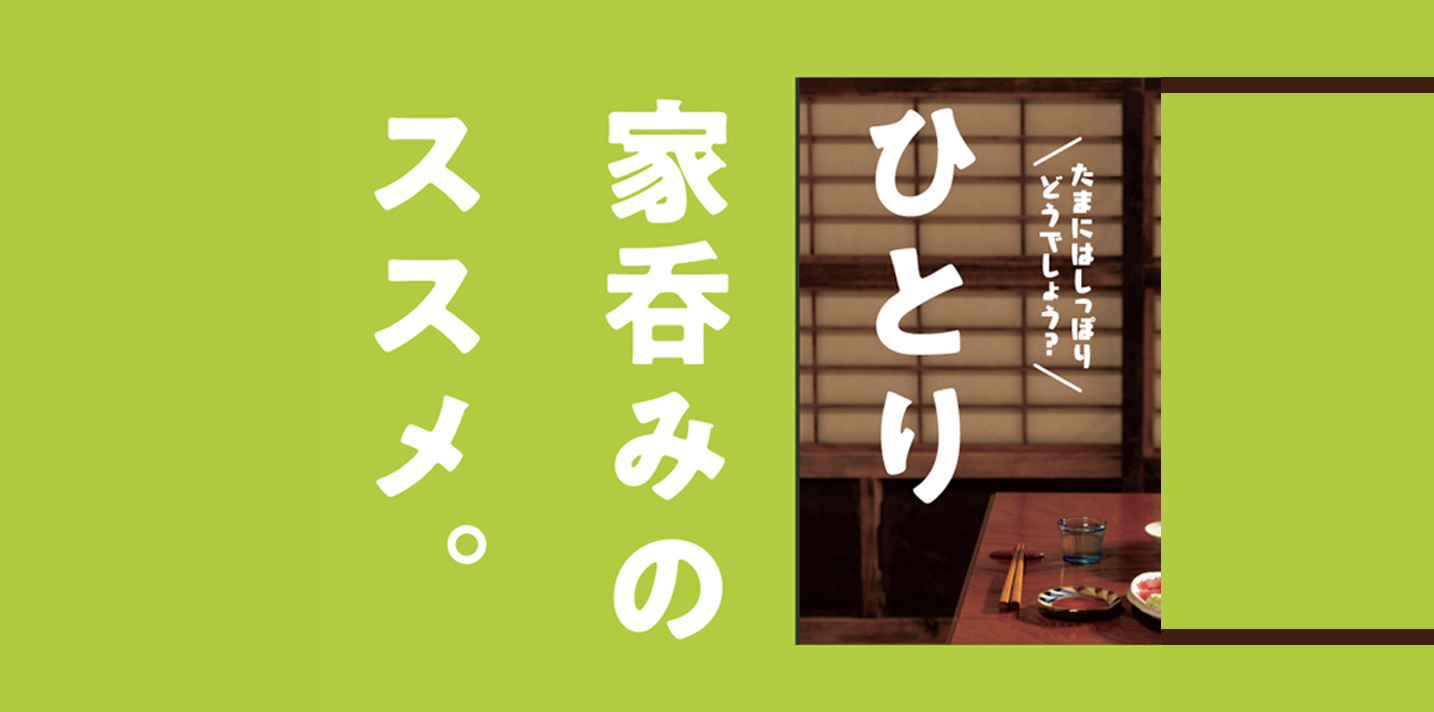日本で唯一の特許を持つ有田焼コーヒーフィルター
佐賀県有田町で作られ、江戸時代から400年以上の歴史をもつ有田焼。日本・アメリカでフィルターの製造特許(コーヒーの油が落ちる、微小なサイズの穴を作る技術)成形に関する特許を取得。有田焼セラフィルターは、コーヒー以外にも水やお茶、日本酒などにも使用することができる。株式会社THREE RIVERSは、そんな伝統的な有田焼の存在を守りつつ、日本唯一の特許を取得した技術を持つコーヒーフィルター「有田焼セラフィルター」を製造している。「有田焼セラフィルター」とは、飲み物を通すだけで味がまろやかになるという魔法の道具だ。"多孔質セラミック"という数ミクロンの穴が無数に空いている素材で作られており、そのセラミックスの力と遠赤外線のW効果によって水のカルキ臭や不純物を取り除く。目に見えないほどの細かい網目で不純物を取り除くことができるため、雑味やえぐみを抑え、まろやかな飲み物が愉しめるという仕組みだ。コーヒーや水道水以外にも、緑茶、焼酎、日本酒やワインなど幅広く使うことができ、日常のあらゆる場面で活躍してくれる。コーヒーを淹れる際に使用するペーパーフィルターとの違いは何か?実は、紙のフィルターでは豆本来の旨味や油分を余計に吸い取ってしまうことがある。しかし、この有田焼セラフィルターは雑味を除きつつも、その旨味や油分を吸い取ることなく存分に抽出してくれる。"コーヒーを淹れる度にペーパーを使う必要が無い"というエコな点も、魅力の一つ。セラフィルターの材料&製造方法複数の原料を独自に配合、こだわり抜いて選んだのは有田の天然の井戸水。機械だけでは実現できなかった成形の調整の半分は人の手で。圧をかけ、窯で焼く時間もしっかり取って、手間をかけている。セラフィルターは多孔質のセラミックでできている陶磁器の一種。その多孔質セラミックは工業製品として、浄水器や空気清浄機のフィルター、車のマフラーの触媒など、多岐にわたり使用されている。有田焼セラフィルターの製造方法は、まずは原料を混ぜることから始まる。地元有田で湧く天然の井戸水を入れながら、素材となる土を作っていく。土ができたら、実際に型に入れて成形。成形工程は微妙な力加減や調整が肝になるため、機械化はできず人の手で行われる。職人の丁寧な手仕事が有田焼セラフィルターを支えているのだ。そしてその後、機械によって十分に圧をかけることで形が完成する。ここで、ようやく窯入れに移る。そこから数十時間という通常の倍の時間をかけて焼いていくのだが、繰り返し使える強度を持つ理由がそこに隠されている。当然どの工程も飛ばすことはできない。「手間をかけてでも良いものを作りたい」という企業と職人のこだわりが詰まっている証拠だ。代表の想いTHREE RIVERS代表の三河さん。新しい商品を誕生させたいという意欲は尽きない。熟練の職人さんが手塩にかけて、丁寧に作り上げる有田焼セラフィルター。「高級品として改まって使われるのではなく、日常生活の中で活躍させたい。」そんな想いが込められている。「手間がかかる、今までにない手順がある。逆に、今まで常識とされていた工程がない。そんな新しい製造方法は職人さんに嫌われてしまうし、専用の道具もないので、誰もやりたがらなかった。でも、私達は世の中にまだないものを作りたい。苦労だって面白い。」とTHREE RIVERS代表の三河さんは語る。さらに三河さんは続けた。「現在だけではなく未来の日本、世界、そして地球のためにも、セラフィルターを広めていきたい。」まだまだ新しい商品を誕生させるべく、日々精進していく。【商品詳細】商品名:有田焼 セラフィルター価格:3,300円 ~ 4,950円(税込) サイズ:【3点セット】縦14㎝×横18.5㎝×高さ8.5㎝ 【単品001】縦10.8㎝×横10.8㎝×高さ10.5㎝商品の詳細はこちら【関連商品】商品名:有田焼 ダブルウォールカップ 全6色価格:3,300円 (税込) サイズ:縦:10.5㎝×横:10.5㎝×高さ:10㎝商品の詳細はこちら商品名:有田焼 マグカップ 全6色価格:3,630円(税込) サイズ:縦:13㎝×横:13㎝×高さ:11.5㎝商品の詳細はこちら
もっと読む