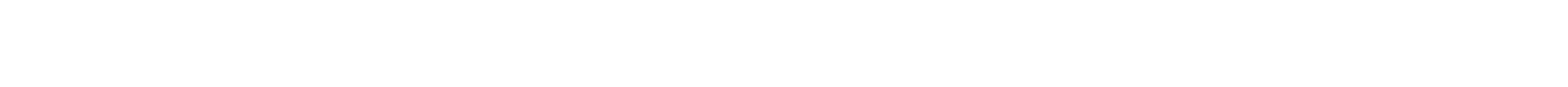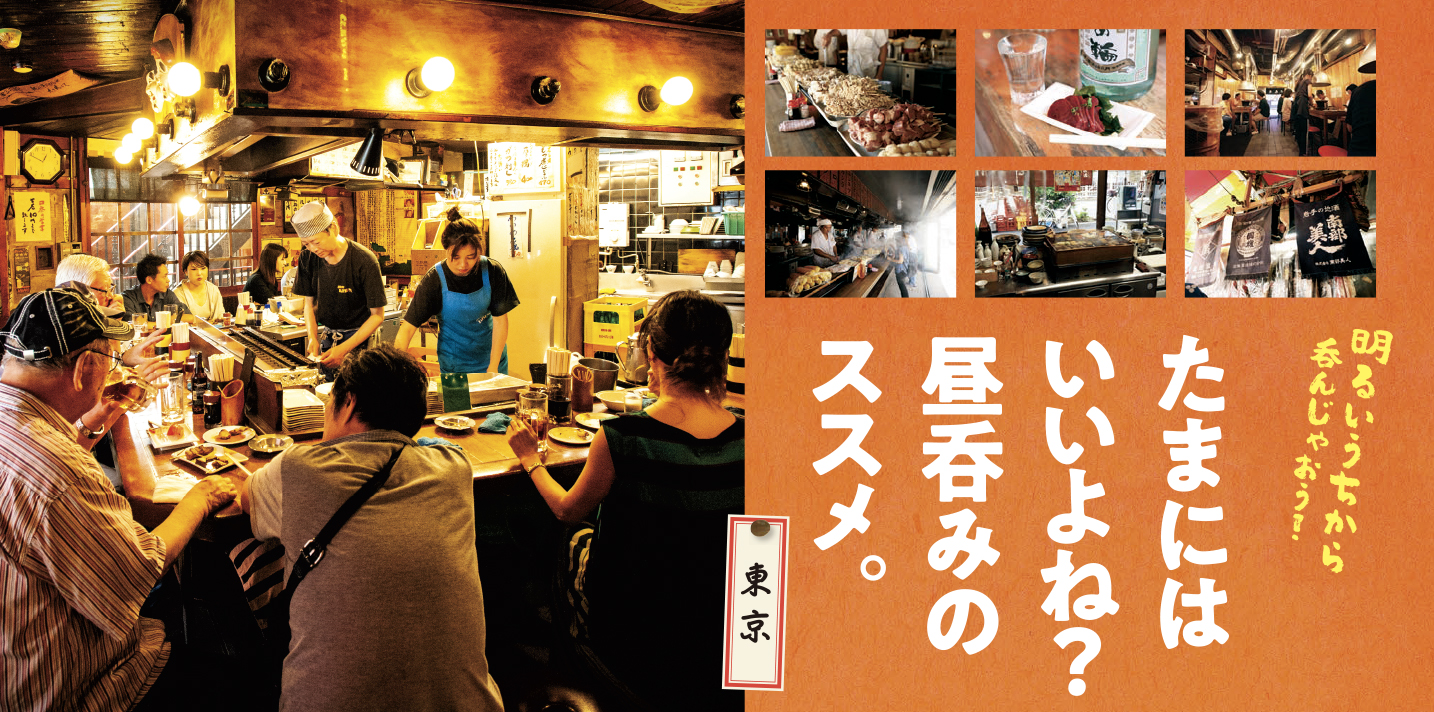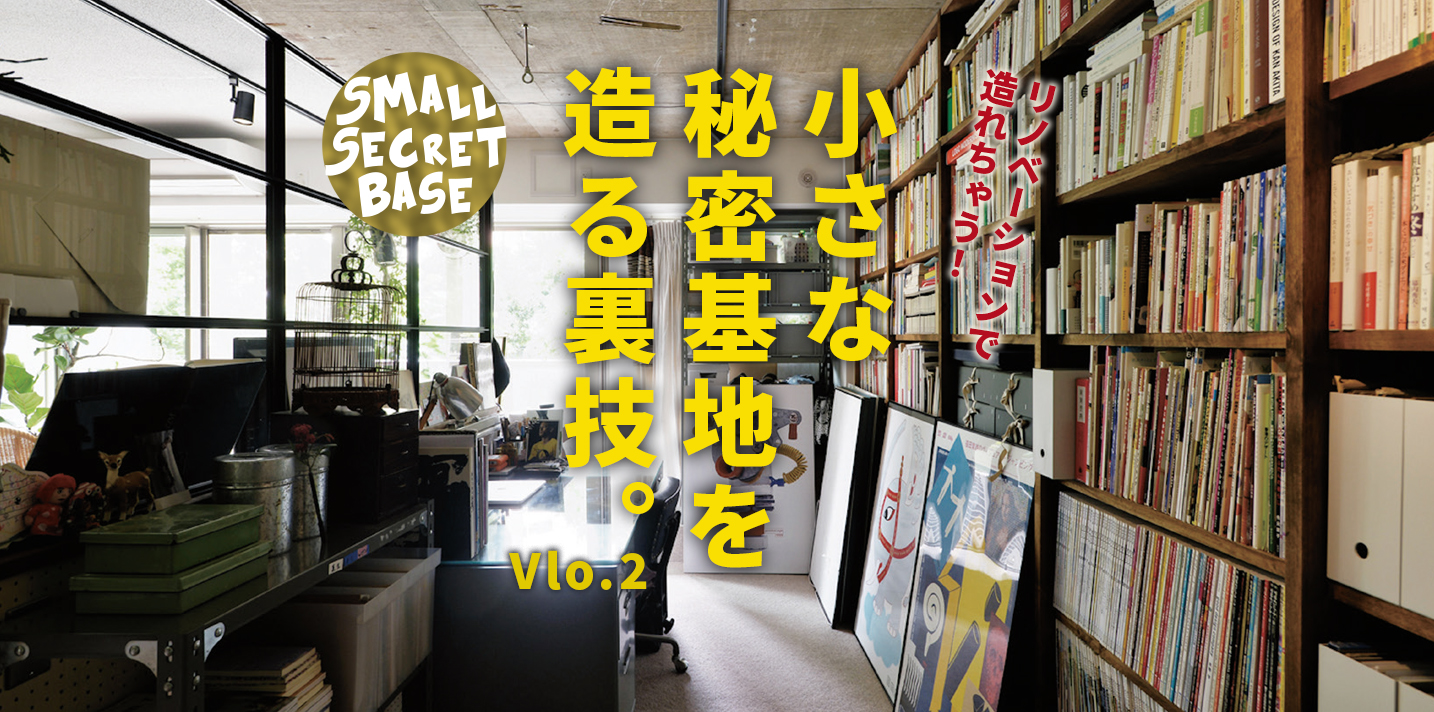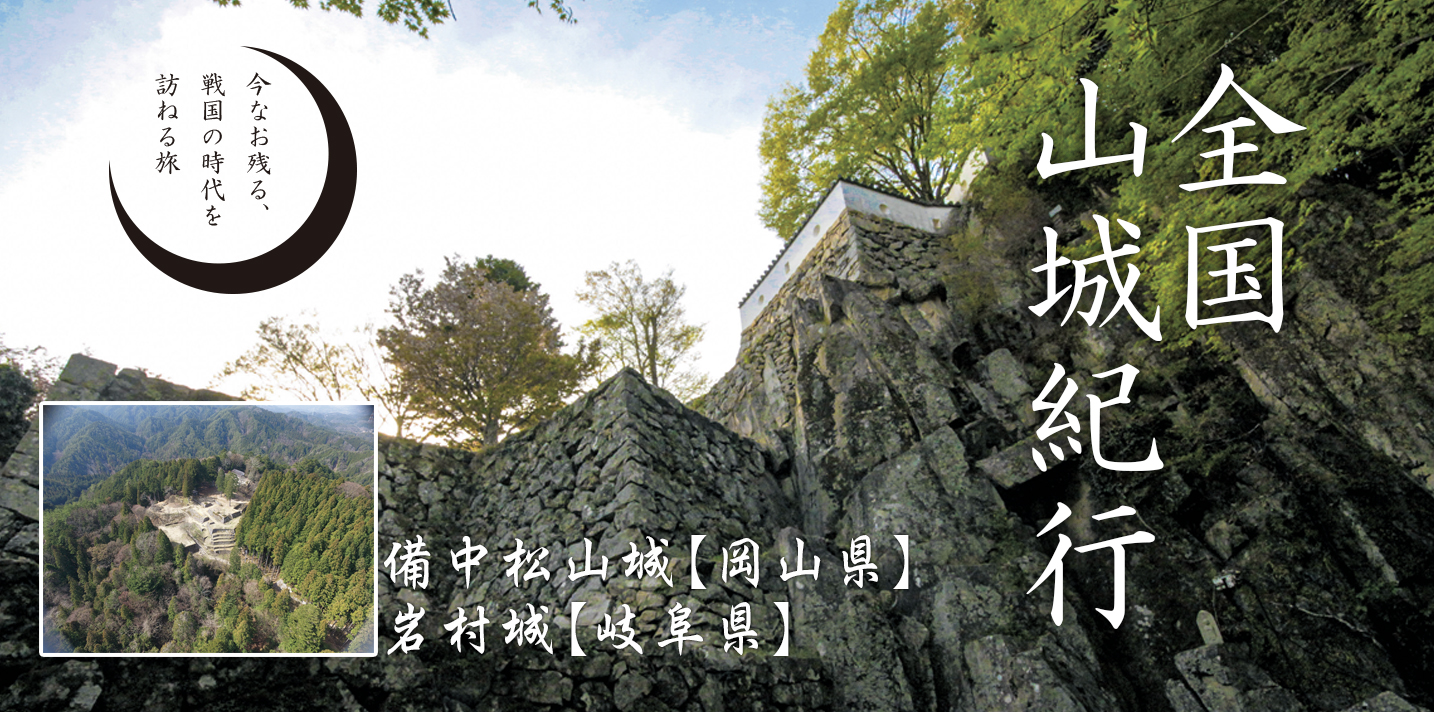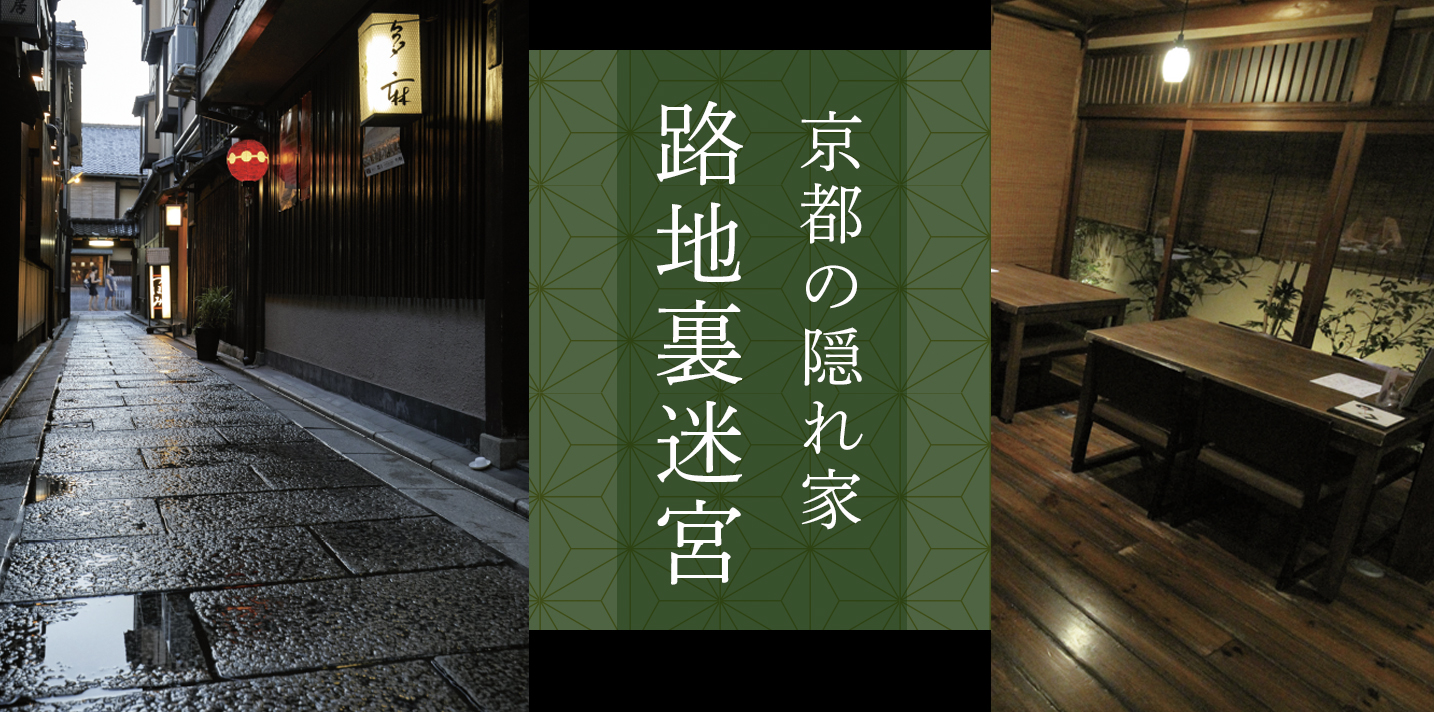子どもの頃の感動を再びその手に【超精密スーパーカー消しゴム】
1970年代後半、多くの子供の手に握られていた「スーパーカー消しゴム」。その人気は瞬く間に拡がり、学校の休み時間には消しゴムを飛ばして遊ぶ子供たちの姿があちこちで見られました。スーパーカー消しゴムという名前を聞くだけでも懐かしく感じますよね。実際に、学校の休み時間はクラスメイトとその強さを競っていたのを思い出します。おもちゃ屋でしかお目にかかれなかったミニカーとは違い、「カー消し」は身近な駄菓子屋で買える手軽さから、あの時代の遊びの相棒として活躍してもらったものです。子供らしい純粋さと、好きなことに対するまっすぐな想いを、あの頃のようにもう一度味わってみませんか?あの感動を再びその手に。スーパーカー消しゴムはおもちゃを持っていけない学校のルールの裏をかいた、画期的なアイテムでした。あくまで消しゴム。カー消しで耳を消す子供はいませんでしたが。今思い出してみると、たくさん持っていたうちの2,3個はとっておけばよかったなと。不思議なくらい、手元に残っていないんですよね。そんな大人の思いを再び叶えるべく、GGF-T社が現代の技術を駆使して、ランボルギーニの名車を超精密に再現した「超精密スーパーカー消しゴム 第1弾 ランボルギーニ」を発売しました。幻のスーパーカー「イオタ」や、スーパーカーの先駆け「ミウラ P400SV」、ポルシェ911の競合として開発された「ウラッコ P250S」など、ランボルギーニ社の歴史を物語る5つの名車が含まれています。各車のディテールは驚くほど精細に再現されており、それぞれの特徴的なデザイン、流線型のスタイル、その存在感を手の中で感じることができますよ。特に、「イオタ」はランボルギーニ「ミウラ」をベースとして試作されたモデルで、事故により1台しか存在しない幻のモデル。車好きにとっては、歴史的にも貴重な車を持つことができるのは、消しゴムだったとしてもちょっとした感動を味わえます。「超精密スーパーカー消しゴム」は、ただの玩具や文房具としての価値だけでなく、「昭和の遊びを現代に蘇らせる」というメッセージが込められています。飾って楽しむのはもちろん、あの頃を思い出して遊んでみるのも楽しいかもしれません。【商品詳細】商品名:超精密スーパーカー消しゴム 第一弾 ランボルギーニ 5個セット価格:2,750円(税込) 商品の詳細はこちら商品名:超精密スーパーカー消しゴム 第二弾 デ・トマソ 4個セット価格:2,200円円(税込) 商品の詳細はこちら商品名:超精密スーパーカー消しゴム 第三弾 マセラティ 5個セット価格:2,750円(税込) 商品の詳細はこちら商品名:超精密スーパーカー消しゴム 第四弾 はたらくクルマ 12個セット価格:3,960円(税込) 商品の詳細はこちら
もっと読む